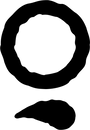エセー
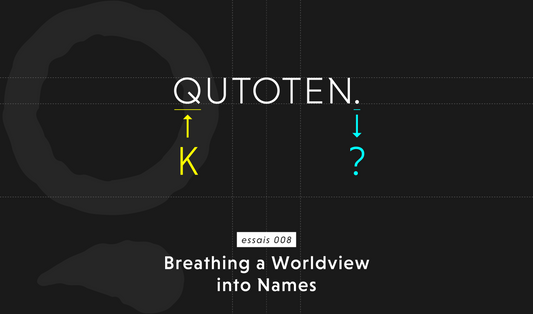
【エセー008】ネーミングで世界観を吹き込む
モノが、感情の栞へ。名前は、意識の羅針盤。 ネーミングとは、そのもの自体に世界観を付与する行為だと考えています。 クールな印象、ふわっとした印象、味わい深い印象、あるいはクスッと笑ってしまうようなユーモラスな印象……。名前が与えるイメージには、実にさまざまな方向性があります。 その名前があることで、使う人の心が前向きになったり、暮らしにささやかなインパクトをもたらしたり。そのように機能したならば、それはネーミングの成功だと言えるでしょう。 QUTOTEN.では、ブランド名やプロダクトの名称にかなりこだわっています。本当はこういう話、いちいち説明せず「粋」にスルーしたいところですが……ちゃんと伝えていかないと埋もれてしまう世の中でもあるので、そのジレンマを、こうしてエセーという形で書き留めておこうとおもいます。 ウイスキー片手にしっぽりと語るような雑談のつもりで、さらっと読んでいただければ嬉しいです。※後半にいくにつれて、徐々にくだけた語り口になりますので、あしからず。笑 最初に名づけたのは「QUTOTEN.」 はじめに名前をつけたのは、ブランド名である「QUTOTEN.(くとうてん)」です。 日本人なら誰もが知る「。」や「、」のことですね。 句読点は文章を読みやすくしたり、リズムをつけたりする効果があります。これをもっと拡大解釈すると、句読点は「余白」を生み出す役割を担っていると捉えることができます。 現代は、インターネットと切り離せない情報過多の時代。 多くの人が、余白の少ない生活を強いられているようにおもいます。 タスクに追われ、通知を気にしながらSNSを無限スクロールし、あちこちで広告が購買意欲を刺激する。 自分と他者の比較で生まれる射幸心は、あらゆる方向から欲望をかき立て、なかなか心が満たされません。 そんな忙しい暮らしに、句読点を打つ。 QUTOTEN.のプロダクトに触れているときくらいは、世間の喧騒を忘れておだやかな時間を過ごしてほしい。 「このお茶、美味しいなあ」とか、「そろそろ鉢を植え替えてみようかな」とか。 そういう類の豊かさって、GDPや経済指数にはなかなか反映されないんですよね。笑 日本人がもつ幸福への感性は、数値化しづらい領域にあるのだとおもいます。 欧米的な「勝利」や「支配」という概念のように、定量的に測れるものばかりではないですから。 日本に旅行で訪れる外国人の多くも、そんな日本の哲学や精神性を体感しに来るのでしょう。 禅や茶道などは、その分かりやすい例ですね。 さて、話が逸れましたが、こうした「余白」を生み出すことが、私たちのブランドの最も深い部分にある根源です。 物質主義の次に来る世界では、こうした日本の美学や思想がいま以上に注目されるだろうと感じていますし、それを世界に向けて発信していきたい。 その想いを「QUTOTEN.」という名称に込めています。 「QUTOTEN.」の字面について ここからは名前の“字面(じづら)”に関する余談です。 非常に些細なことなので、読み飛ばしていただいても大丈夫かもしれません。笑 「くとうてん」をそのままアルファベットで表すと、...
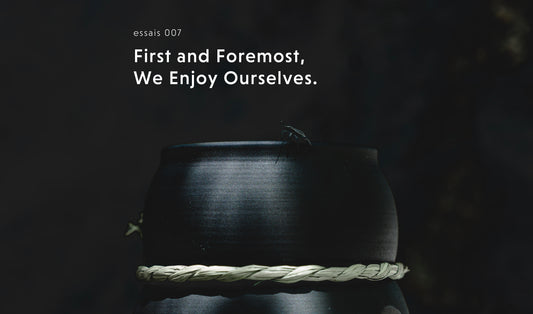
【エセー007】まずは自分たちが楽しむ。
「真剣にやれよ!仕事じゃねぇんだぞ!」 僕が敬愛するタモリ(森田一義)さんの言葉です。 きっとそういうことです。 。、
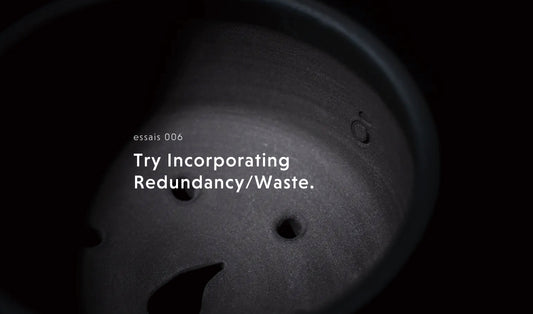
【エセー006】無駄を取り入れてみる。
日本の建築には、床の間(とこのま)という空間あります。 和室における一段高くなっているスペースで、掛軸をかけたり、花を生けたりする空間なのですが、なかなか不思議だとおもいませんか。 日々の暮らしにおいて、床の間が絶対に必要かと言われるとそんなことはないはずです。(今では無い家のほうが多いくらいですね) ご飯をつくったり食べたりするわけでもないし、そこに座って休むこともなく、なにかを収納するわけでもない。 なくても生きてゆける空間にも関わらず、床の間はそこにあります。 それはなぜでしょうか。 。、。、。、 床の間は、心を向ける場所なのだと思います。 なにかが書かれている掛軸、あるいは生けられた草木と同じ空間にいることで、意識が “なんとなく” そこに向きます。 この心の動きを、日本人は大切にしてきたのでしょう。 無用の用。 必要な無駄。 自然な不自然。 「無駄」と「必要」は共存するわけです。 おもしろいですね。 ...
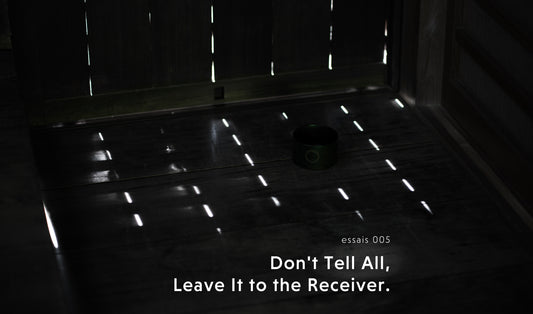
【エセー005】すべてを語らず、受け手に委ねる。
「想像力は、宇宙を包むことができる」 とアインシュタインは言いました。 僕は、人間の想像力に興味があります。 想像力は時間を自由に行き来することができ、空間に囚われることもなく、光のスピードさえも超えます。 物事を説明することは、理解への難易度を下げることができますが、同時に想像力に縛りを掛けます。 100の理解まで引き上げることはできても、120の世界に到達するためには想像力が必要です。 。、。、。、 原作を読んだことのある作品の映画を観て がっかりした経験はありませんか? 僕は何度もあります。笑 自分の頭の中で無限に広がっていた色彩は、いざ映像化されると途端に色褪せてしまい、あんなにもキラキラと輝いていた美しいイメージは幻へと消えて去ってしまいます....(すべての作品とは言いませんが) 作曲するときも同じことに陥りやすいのですが、これは脳内のイメージを具現化するときのジレンマと言えますね。 。、。、。、 現代社会においては具体的にすることが好まれるようですが、抽象的な状態のほうがずっと自由で楽しいはず、というのが僕の仮説です。 俳句が森羅万象を表現できるのは、5・7・5という限られた音数のなかに、そもそもすべてを詰め込もうとしていないからです。 蓮根の穴に時空の歪みあり(平夜繭) ...
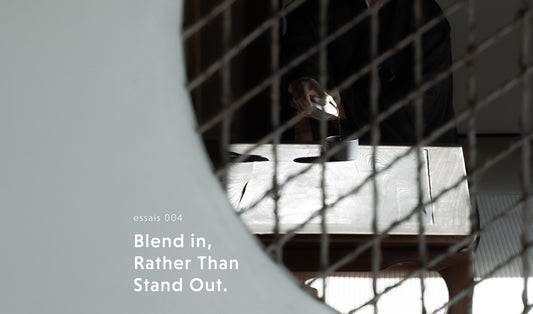
【エセー004】目立つのではなく、溶け込む。
“晴れと褻(ハレとケ)” という言葉をご存知でしょうか。 晴れとは、非日常のこと。 「晴れ着」「晴れ舞台」などの言葉があるように、冠婚葬祭や行事ごと、特別な日を指します。 褻とは、日常のこと。 ごくごく普通で、変わり映えのない生活を指します。 当然ながら、暮らしの大部分を占めるのは、「褻」です。 しかし、SNSの普及によって、僕たちは毎日のように「だれかの晴れ」を間接的に目撃するにするようになりました。 個人にとってたまにしかない非日常も、世界中のあらゆるタイミングで、晴れの出来事は起きているわけです。 (毎日新しい命が生まれ、死ぬように) そして、だれかの晴れの情報が日常的に入ってくるようになると、ひとは自分の今日さえも特別なものにしたがる傾向があるようです。 ただ、晴れというのはエネルギーを使います。 慣れていないことをするわけですから。 それが毎日となると、疲れます。 ちょうど、毎日背伸びをしながら歩いているようなものです。 QUTOTEN.の哲学に 「目立つのではなく、溶け込む。」 を入れたのは、 褻のなかにも豊かさがあり、...
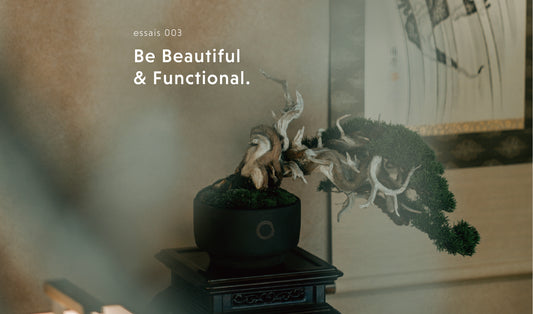
【エセー 003】美しく、機能的である。
僕は、飛行機の形が好きです。 なぜかというと、 あれは人間が考えうる最も機能的な形だとおもうからです。 もし、飛行機がかっこよさを求めたらどうでしょうか? 翼の形を無理に変えたり、必要のない装飾を施したり。 そんなことをしたら、安全面が下がってしまいます。 そんな飛行機には乗りたくないですよね。 飛行機は、最も安全な飛行ができる形を追求しています。 だから、どの航空会社の飛行機もだいたい同じ形をしています。 全人類が共通して「ベスト」の形と認識しているということです。 そして、これからもっと機能的な形にアップデートしていくことでしょう。 この姿勢は、ものづくり全般に言えることだとおもいます。 「機能美を追求すればするほど自然に近づいていく」 というのが僕の持論です。 飛行機の例のように、機能美を追求することは、自然法則を味方にすることです。 そしてQUTOTEN.でつくるプロダクトは、 見た目のよさ以上に、機能性を重視しています。 水が流れやすい角度、穴の大きさ、高台の高さ、肌に触れるときの質感、重み。 建築家のアントニ・ガウディがこんなことを言っていました。 「私たちが読み解くよう努力しなければいけないものは自然である。その偉大なる本はつねに開かれている。」 自然という偉大な本から人類が読み解いた知恵は、まだ宇宙における一握の砂。 QUTOTEN.は、自然に近づいていくようなものづくりを追求します。 。、

【エセー 002】自然体である。
自然体ってなんでしょう。 そもそも、自然ってなんでしょう。 悠然と佇む山々。 鬱蒼と木々が生い茂る森。 清らかに流れてゆく川、その水が流れ込む海。 雲が浮かぶ空、雨、雪、雷。 春夏秋冬、季節の移ろい。 この地球に存在する物理的な意味での自然。 あるいは、精神的な意味での自然。 あるがままに生きる。 背伸びしないこと。 ふるまいに違和感がないこと。 無理がなく、リラックスしている状態。 抽象的であいまいだけど、 心地よさがある言葉。 具体的な定義を決めるのは野暮ですね。 ことばで表現できることはあまりに限られています。 『自然体である』という哲学には、 どこにいても、なにをしていても、 「うん、大丈夫だ」とおもえる御守りのような力があります。 QUTOTEN.から、 そういう力が生まれることを目指して。 。、

【エセー 001】Tradition is Transition.
伝統には、「古いもの」というイメージがあるかもしれません。 しかし、僕たちは伝統に対して「新しいもの」と定義しています。 なぜならば、伝統として残ってきた技術やノウハウは、つねに時代のニーズを掴まえ続け、柔軟に形を変えてきた結果だからです。 鋳金の人間国宝である大澤光民氏が、こんなことを言っていました。 「伝統とは、絶えず新しいものである」 光民氏の作品は、鋳金という長く続く技術を継承しながらも、非常にモダンな印象を受けます。 高度な技術に裏付けられた、きめ細やかなで迷いのない模様。 線の一本一本から、光民氏の人間性が垣間見えます。 伝統と深く向き合っていると自ずとこのような創作性が出て、結果的に新しくなっていくのかもしれません。 挑戦の先に、新しいものが生まれます。 技術やノウハウもまた然り。 偶然の出来事から生まれた現象が、ときに形を成すこともあります。 それらが地層のように積み重なってきたのが伝統ならば、いま地表に出ている伝統が、その最高到達地点だと考えるとなんだか心躍りませんか。 挑戦すれば失敗するし、新しいものはときに批難を浴びる。 それでも、伝統と関わりたいから。 Tradition is Transition. (伝統とは、絶えず新しいものである) そんなことを考えながら、QUTOTEN.は 日本の伝統の素晴らしさを発信していきます。 。、
Featured collection
-
 SOLD OUTSOLD OUT
SOLD OUTSOLD OUT -
-
 SOLD OUTSOLD OUT
SOLD OUTSOLD OUT -
-
 SOLD OUTSOLD OUT
SOLD OUTSOLD OUT -
 SOLD OUTSOLD OUT
SOLD OUTSOLD OUT -
 SOLD OUTSOLD OUT
SOLD OUTSOLD OUT -
 SOLD OUTSOLD OUT
SOLD OUTSOLD OUT